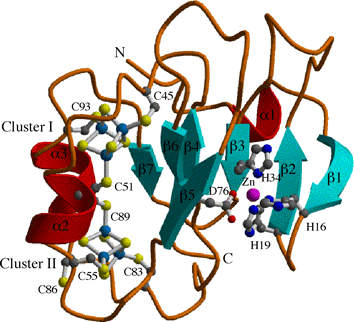 |
| Sulfolobus sp. strain 7由来フェレドキシンの分子構造 |
|
鉄硫黄クラスターの鉄原子を灰色、硫黄原子を緑色で示している。システイン残基が鉄原子に結合することで、鉄硫黄クラスターを固定している。 亜鉛原子を紫色で示している。His16・His19・His34・Asp76の4残基が亜鉛原子に正四面体配位をしている。亜鉛原子を含むフェレドキシンは本構造解析によって初めて発見された。この亜鉛原子は、耐熱性獲得のための構造保持に使用されていると考えられる。 |
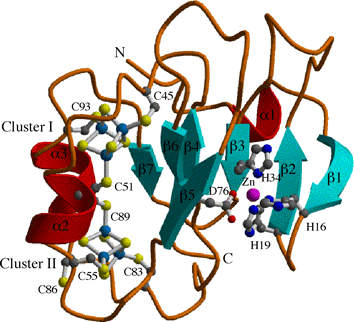 |
| Sulfolobus sp. strain 7由来フェレドキシンの分子構造 |
|
鉄硫黄クラスターの鉄原子を灰色、硫黄原子を緑色で示している。システイン残基が鉄原子に結合することで、鉄硫黄クラスターを固定している。 亜鉛原子を紫色で示している。His16・His19・His34・Asp76の4残基が亜鉛原子に正四面体配位をしている。亜鉛原子を含むフェレドキシンは本構造解析によって初めて発見された。この亜鉛原子は、耐熱性獲得のための構造保持に使用されていると考えられる。 |
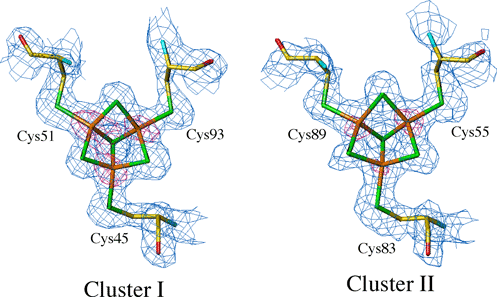 |
| 鉄硫黄クラスター部分の電子密度図 |
|
鉄硫黄クラスターの鉄原子をオレンジ色、硫黄原子を緑色で示している。赤いピークは波長1.542Åで計算したバイフット差フーリエ図であり、この波長で異常分散効果の大きな鉄原子位置にピークが表示されている。これらのことからクラスターIとクラスターIIはともに[3Fe-4S]型であることがわかる。 |
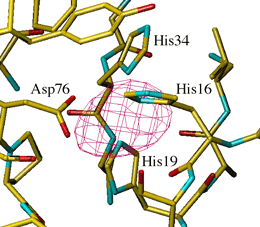 |
| 異常分散効果を利用した亜鉛原子の同定 |
| 構造解析の途中で、His16・His19・His34・Asp76の4つの残基で囲まれる大きな電子密度の塊が見つかった。各残基の配位様式からこれが亜鉛原子であると仮定し、亜鉛原子の吸収端(波長1.283Å)前後の波長のX線を使用し回折強度データを収集した。波長1.275Åで収集したデータを使用したバイフット差フーリエ図では赤いピークが現れたが、波長1.290Åで収集したデータでは現れなかった。これらのことにより、波長に依存した異常分散効果の違いを利用して亜鉛原子であることを同定することができた。 |