研究室スタッフが2003年以前に取り組んだ研究の成果を簡単に紹介します。
超巨大磁気抵抗(CMR)材料 島川教授がNEC基礎研究所で取り組んだテーマです。
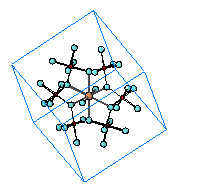 磁場の変化に応じて電気抵抗が大きく変化する物質「磁気抵抗効果材料」は、磁気記録の読み取りヘッドや将来のスピントロニクスの材料として期待されています。
90年代の半ばから、ペロブスカイト構造Mn酸化物(La,Sr)MnO3がそれまでに知られた磁気抵抗効果を遥かに凌ぐ「超巨大磁気抵抗」を示すことで注目を集めていました。
一方、島川教授を含むNECの研究グループは、ペロブスカイト酸化物とは結晶構造も電子状態も異なるパイロクロア構造Mn酸化物で、ペロブスカイト酸化物に見られたものと同様のCMRが現れることを見出しました。
磁場の変化に応じて電気抵抗が大きく変化する物質「磁気抵抗効果材料」は、磁気記録の読み取りヘッドや将来のスピントロニクスの材料として期待されています。
90年代の半ばから、ペロブスカイト構造Mn酸化物(La,Sr)MnO3がそれまでに知られた磁気抵抗効果を遥かに凌ぐ「超巨大磁気抵抗」を示すことで注目を集めていました。
一方、島川教授を含むNECの研究グループは、ペロブスカイト酸化物とは結晶構造も電子状態も異なるパイロクロア構造Mn酸化物で、ペロブスカイト酸化物に見られたものと同様のCMRが現れることを見出しました。
[ 代表的な論文 ]
"Giant magnetoresistance in Tl2Mn2O7 with the pyrochlore structure", Y. Shimakawa, Y. Kubo, and T. Manako, Nature 379, 53 (1996).
"Crystal structure, magnetic and transport properties, and electronic band structure of colossal magnetoresistance Tl2Mn2O7 pyrochlore", Y. Shimakawa and Y. Kubo, Mat. Sci. Eng. B 63, 44 (1999).
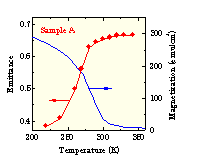 ペロブスカイト構造CMR酸化物が示す室温付近での大きな電気抵抗の変化に注目した新しいデバイス「熱放射率可変素子」を提案し、その機能を実証しました。
金属−絶縁体転移に伴って、熱赤外領域での放射率が変化することを利用して、人工衛星の熱制御を行うものです。
この素子はSmart Radiation Device (SRD)として、2003年5月に宇宙科学研究所より打ち上げられた小惑星探査衛星MUSES-C(はやぶさ)に搭載されています。
ペロブスカイト構造CMR酸化物が示す室温付近での大きな電気抵抗の変化に注目した新しいデバイス「熱放射率可変素子」を提案し、その機能を実証しました。
金属−絶縁体転移に伴って、熱赤外領域での放射率が変化することを利用して、人工衛星の熱制御を行うものです。
この素子はSmart Radiation Device (SRD)として、2003年5月に宇宙科学研究所より打ち上げられた小惑星探査衛星MUSES-C(はやぶさ)に搭載されています。
[ 代表的な論文 ]
"A variable-emittance radiator based on a metal-insulator transition of (La,Sr)MnO3 thin films", Y. Shimakawa, T. Yoshitake, Y. Kubo, T. Machida, K. Shinagawa, A. Okamoto, Y. Nakamura, A. Ochi, S. Tachikawa, and A. Onishi, Appl. Phys. Lett. 80, 4864 (2002).
強誘電体材料 島川教授がNEC基礎研究所で取り組んだテーマです。
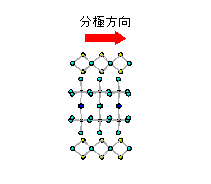 強誘電体を利用した新しいメモリ(FeRAM)に間する研究開発が近年活発になってきています。
しかしながら、薄膜デバイスの研究に比べ、物質研究はあまり進んでいませんでした。
そこで、高分解能中性子回折による精密な結晶構造解析から、FeRAMに用いられる強誘電体材料の分極特性を明らかにしました。
強誘電体を利用した新しいメモリ(FeRAM)に間する研究開発が近年活発になってきています。
しかしながら、薄膜デバイスの研究に比べ、物質研究はあまり進んでいませんでした。
そこで、高分解能中性子回折による精密な結晶構造解析から、FeRAMに用いられる強誘電体材料の分極特性を明らかにしました。
[ 代表的な論文 ]
"Crystal structures and ferroelectric properties of SrBi2Ta2O9 and Sr0.8Bi2.2Ta2O9", Y. Shimakawa, Y. Kubo, Y. Nakagawa, T. Kamiyama, H. Asano, and F. Izumi, Appl. Phys. Lett. 74, 1904 (1999).
"Crystal structure and ferroelectric properties of ABi2Ta2O9 (A=Ca, Sr, and Ba)", Y. Shimakawa, Y. Kubo, Y. Nakagawa, S. Goto, T. Kamiyama, H. Asano, and F. Izumi, Phys. Rev. B 61, 6559 (2000).
無限層構造超伝導体 東助教授が高野研究室で取り組んだテーマです。
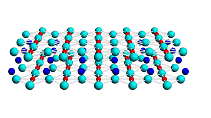 高温超伝導が発現するための最も単純な構造と考えられていた無限層構造を持つACuO2(A:アルカリ土類金属)とその関連物質の高圧合成に取り組み、その過程で、110Kもの高い転移温度を持つ超伝導体が存在することを見出しました。
この物質は高圧下で合成されます。新物質探において高圧合成が極めて有力な手法であること示す結果と言えます。
高温超伝導が発現するための最も単純な構造と考えられていた無限層構造を持つACuO2(A:アルカリ土類金属)とその関連物質の高圧合成に取り組み、その過程で、110Kもの高い転移温度を持つ超伝導体が存在することを見出しました。
この物質は高圧下で合成されます。新物質探において高圧合成が極めて有力な手法であること示す結果と言えます。
[ 代表的な論文 ]
"Superconductivity at 110K in the infinite-layer compound (Sr1-xCax)1-yCuO2", M. Azuma, Z. Hiroi, M. Takano, Y. Bando, and Y. Takeda, Nature 356, 6372 (1992).
スピン梯子格子化合物 東助教授が高野研究室で取り組んだテーマです。
 SrCu2O3とSr2Cu3O5がスピン梯子格子を含む典型物質であることを実験的に明らかにしました。
スピン梯子格子は、理論的に厳密な取り扱いが可能な1次元鎖と、高温超伝導の舞台である2次元面をつなぐ系として、理論先行で研究が進み、スピンギャップの存在やキャリアドーピングによる超伝導化の可能性が予言されていた材料です。
東助教授を中心とした研究により、スピン梯子格子化合物の理論的予言を実験的に検証する道が開かれました。
SrCu2O3とSr2Cu3O5がスピン梯子格子を含む典型物質であることを実験的に明らかにしました。
スピン梯子格子は、理論的に厳密な取り扱いが可能な1次元鎖と、高温超伝導の舞台である2次元面をつなぐ系として、理論先行で研究が進み、スピンギャップの存在やキャリアドーピングによる超伝導化の可能性が予言されていた材料です。
東助教授を中心とした研究により、スピン梯子格子化合物の理論的予言を実験的に検証する道が開かれました。
[ 代表的な論文 ]
"Observation of a spin-gap in SrCu2O3 comprising spin-1/2 quasi-1D two-leg ladders", M. Azuma, Z. Hiroi, M. Takano, K. Ishida, and Y. Kitaoka, Phys. Rev. Lett. 73, 3463 (1994).
"Disappearance of the spin gap in Zn-doped 2-leg ladder compound Sr(Cu1-xZnx)2O3", M. Azuma, M. Takano, and R.S. Eccleston, J. Phys. Soc. Jpn. 67, 740 (1998).
高圧合成 東助教授が高野研究室で取り組んだテーマです。
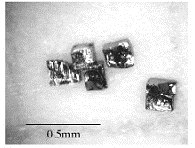 高圧合成法は、今までにない興味深い物性を示す物質を創製するユニークな手法です。
東助教授を中心として、高輝度の放射光白色X線を用いて高温高圧下の粉末X線回折実験を行い、その直接観察を基に単結晶を育成するという手法を新たに開発しました。
高圧合成法は、今までにない興味深い物性を示す物質を創製するユニークな手法です。
東助教授を中心として、高輝度の放射光白色X線を用いて高温高圧下の粉末X線回折実験を行い、その直接観察を基に単結晶を育成するという手法を新たに開発しました。
[ 代表的な論文 ]
"Observation of a spin-gap in SrCu2O3 comprising spin-1/2 quasi-1D two-leg ladders", M. Azuma, Z. Hiroi, M. Takano, K. Ishida, and Y. Kitaoka, Phys. Rev. Lett. 73, 3463 (1994).
"Disappearance of the spin gap in Zn-doped 2-leg ladder compound Sr(Cu1-xZnx)2O3", M. Azuma, M. Takano, and R.S. Eccleston, J. Phys. Soc. Jpn. 67, 740 (1998).
高温超伝導酸化物の相図 池田助手が取り組んだテーマです。
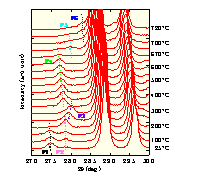 Bi系超伝導体の一つBi2Sr2CuO6は組成と構造の単純さから、高温超伝導のモデル物質と考えられていました。
しかしながら、詳細な相図研究から、この物質には酸素量の僅かな違いにより少なくとも6つの相が存在することが明らかになりました。
この中にはTc=26 Kと従来の報告よりも遥かに高い転移温度を示す相があることも明らかになりました。
Bi系超伝導体の一つBi2Sr2CuO6は組成と構造の単純さから、高温超伝導のモデル物質と考えられていました。
しかしながら、詳細な相図研究から、この物質には酸素量の僅かな違いにより少なくとも6つの相が存在することが明らかになりました。
この中にはTc=26 Kと従来の報告よりも遥かに高い転移温度を示す相があることも明らかになりました。
[ 代表的な論文 ]
"Thermal stability, structural features, and electromagnetic properties of Bi2+xSr2-xCuO6+d", T. Niinae, Y. Ikeda, Y. Bando, M. Takano, Y. Kusano, and J. Takada, Physica C 313, 29 (1999).
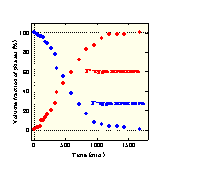 Pr2-xLaxCuO4固溶体は高温での焼成によりT型結晶構造をとります。
そころが、一般にはイオン拡散の起こりにくい室温においても、数分〜数時間の時間スケールで結晶構造がT'型に変化するという奇妙な振る舞いを見出しました。
これは、ミクロな電子相分離とも関係するかもしれない興味深い現象です。
Pr2-xLaxCuO4固溶体は高温での焼成によりT型結晶構造をとります。
そころが、一般にはイオン拡散の起こりにくい室温においても、数分〜数時間の時間スケールで結晶構造がT'型に変化するという奇妙な振る舞いを見出しました。
これは、ミクロな電子相分離とも関係するかもしれない興味深い現象です。
[ 代表的な論文 ]
"A new tetragonal phase in La-lich Pr2-xLaxCuO4", Y. Ikeda, K. Yamada, Y. Kusano, and J. Takada, Physica C 378-381, 395 (2002).