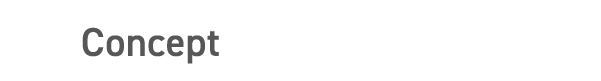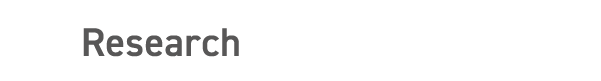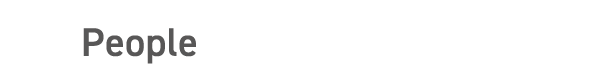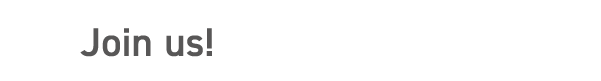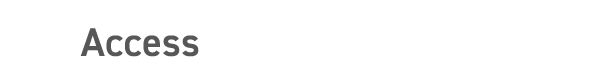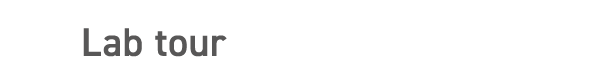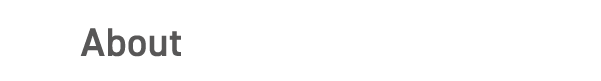Research
真核生物には、外部環境情報を受容体が受け取ったのちに、核でその情報を遺伝子発現に転換する仕組みがあります。核は、さまざまな物質が高密度に詰まっていて、極めて混雑した状態であると考えられています。このような核において、外部情報がどのような「情報ハブ」を介して、必要な遺伝子群のオン・オフを実現して、生理現象につなげているのか、その「核内情報制御機構」は未だに解明されていません。
そこで、私たちは、モデル植物のシロイヌナズナ(Arabidopsis thaliana)を材料に用いて、環境変化に応答して細胞や組織が形作られる時、どのような制御が核や細胞内で繰り広げられているのか、分子生物学的に解明しています。

 遺伝子発現制御機構の解明
遺伝子発現制御機構の解明
遺伝子発現制御機構を研究するモデルとして、光環境変化に応答する可塑的な形態形成過程に着目しています。たとえば、明暗に応答する形態形成は、光受容体から一連の光情報伝達経路を介して、核内の遺伝子発現の制御の元で実行される生理反応です。私たちはこの時に核の中で、環境情報が遺伝子発現に転換される核内情報制御機構に興味を持っています。

 植物細胞の形態形成を制御するメカニズムの解明
植物細胞の形態形成を制御するメカニズムの解明

植物はさまざまな形の細胞により構成されています。根毛や花粉管など、典型的な先端成長のみによって形成される細胞を研究対象として、細胞極性の確立と維持に注目して研究しています。
 遺伝子発現制御機構の解明
遺伝子発現制御機構の解明
生物を取り巻く環境は常に変化している。その変化に対応するため、生物に備わっている仕組みを解明しています。具体的には、核内に存在する8サブユニットで構成されるCOP9
signalosomeタンパク質複合体(CSN)に注目してきました。CSNは動物から植物まで広く存在しており、動物では飢餓やDNA損傷などに応答し、植物では光の有無に応答することを明らかにしてきました。
私たちはCSNによる核内情報伝達を解析するモデルとして、シロイヌナズナを実験材料に用いて研究を行なっています。植物は環境の変化に応答するとき、受容体に始まり、遺伝子の発現制御を介して、生理現象を引き起こする一連の制御メカニズムが駆使します。遺伝子の発言を制御する仕組みには、遺伝子転写を司る転写因子の「量的制御」とともに、すでに転写されている産物に対する「質的制御」が行なわれます。私たちはCSNが、この多段階的な制御機構の鍵因子として働くと考えています。CSNの中でも特にCSN5サブユニットは、タンパク質分解を制御する「量的制御」の鍵となる因子です。一方、CSN1サブユニットは、spliceosomeやcleavage
factor
Iなどの複合体と結合して、転写抑制機能を保有しています。このことからCSN1サブユニットは転写産物のprocessing制御を通して、「質的制御」を行なっていると考えています。
私たちは植物の可塑的な形態形成を制御する仕組みを解明することで、広く生物に保存される、普遍的な遺伝子発現制御機構を解明できると考えて研究を進めています。このようなダイナミックな制御機構を、植物をモデルに展開するユニークなアプローチに興味がある学生や研究員の方はぜひ見学にいらしてください!
 植物細胞の形態形成を制御するメカニズムの解明
植物細胞の形態形成を制御するメカニズムの解明
植物細胞は、個体や器官においてそれぞれが果たす機能を反映した多様な形態を有しています。またその形態は個体や器官の形を決める重要な因子でもあります。植物細胞の変化に富んだ形は、一般に細胞全体または部分領域が一様に拡張する拡散成長と細胞壁や細胞膜の生成が常に先端のみで起こることにより細胞の一部が伸長する先端成長の組み合わせによって生み出されます。その中で先端成長は、植物細胞の複雑かつ精緻な形態を生み出すために欠かせないものであり、細胞極性の確立・維持という観点からも精力的に研究されてきました。我々の研究室では、典型的な先端成長のみによって形成される根毛と花粉管を研究材料とし、その形成過程における平面内極性の確立、および先端極性の維持に関わる分子機構の解明を目指しています。特に、ホスホイノシチドなどのリン脂質が植物細胞の形態形成においてどのような役割を果たすのか、その制御的役割の解明を目指し研究を進めています。
研究キーワード:
植物細胞形態形成、根毛、花粉、ホスホイノシチド、遺伝学、共焦点
レーザー顕微鏡
 その他の研究
その他の研究
・ビワの花が香る分子機構の解明 (所内共同研究)
周囲に花がない厳冬の時期、ビワの花は甘い香りを放ちます。「植物好き」という接点で繋がった化学研究所の3人は、それぞれの専門を活かして、ビワの花の香気成分の制御機構の解明に挑戦しています。
K.U.RESEARCH Vol.122018/03/24
「香りを追って異分野ユニット」
-

Koeduka T, Fujita Y, Furuta T, Suzuki H, Tsuge T, Matsui K. Aromatic amino acid decarboxylase is involved in volatile phenylacetaldehyde production in loquat (Eriobotrya japonica) flowers. Plant Biotechnol, (Tokyo), 34, 193-8 (2017). [Pubmed]
-

*Koeduka T, Kajiyama M, Furuta T, Suzuki H, Tsuge T, Matsui K., Characterization of an O-methyltransferase specific to guaiacol-type benzenoids from the flowers of loquat (Eriobotrya japonica). J Biosci Bioeng 122, 679-84 (2016). [Pubmed]
-

*Koeduka T, Kajiyama M, Suzuki H, Furuta T, Tsuge T, Matsui K., Benzenoid biosynthesis in the flowers of Eriobotrya japonica: molecular cloning and functional characterization of p-methoxybenzoic acid carboxyl methyltransferase. Planta 244, 725-36 (2016). [Pubmed]
・お茶の起源を求めて
現在の宇治茶は、江戸時代中期に宇治田原町の永谷宗園が日本緑茶の製法の基礎を築いたおかげです。この地にゆかりあるお茶の起源を求めて、日中韓の比較研究を通して宇治茶のルーツ探しに挑戦しています。
-

Cho KH, Jo A, Tsuge T, Kim JC, Kim R, Yoon HS, *Kim GT., Comparative analysis of local green tea in Korea by STS-RFLP. J Life Sci 20, 1415-9 (2010).
-

Cho KH, Lee EJ, Tsuge T, Jo A, Kim JC, Cheong GW, Yoon HS, *Kim GT., Comparative genomic analysis of Korean and Japanese green tea trees by using molecular markers. Can J Plant Sci 90, 293-8 (2010).